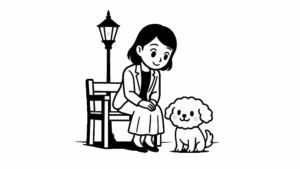強迫性障害と過ごしてきた時間の中から、今も時折思い出すワンシーンを綴っています。
家に帰って、カバンを床に置くだけ――そのはずなのに、その日の私は玄関でカバンを持ったまま動けなかった。腕の重さはじわじわ増していくのに、足だけが行き先を決められない。カバンの底は床すれすれで揺れていて、あと数センチ下ろせば肩の力も抜けるはずなのに、その「数センチ」がどうしても遠かった。
理由は単純で、外出中にカバンが“汚れた”と思う出来事があったからだ。それも、人が聞けばきっと笑って流すような、ほんの些細なこと。それなのに、私の中では世界がきれいに二層に割れてしまった。嫌悪と安心。汚れと清潔。触れていい領域と、触れたくない領域。玄関という境界線の上で、私はどちらの側にも踏み出せず、ただ立ち尽くしていた。
カバンを宙づりにしたまま、私は“考える”というより“無限ループの会議”を開いてしまう。出席者は、混乱している私と、一刻も早くこの状況から逃れたい私。議題は「このカバン、どこに着地させるか」。意見だけは次々に飛び交うのに、肝心の結論だけが永遠に出てこない。会議室の真ん中で立ち尽くしている私は、ただひとり消耗していく。
昨日までの私なら、こんな会議はそもそも開催されていなかった。仕事から帰ってきてソファにカバンを放り投げ、その上にスマホや財布を重ねても、少なくともそれで立ち止まることはなかった。なのに今の私は、嫌なものに触れた“気がする”だけのカバンをどう扱うか――それだけのことで、丸一日ぶんのエネルギーを使い果たしてしまう。
玄関の静けさに、時計の秒針だけがカチ、カチと響いていた。その音に背中を押されるように壁の時計へ視線を向けると、針は19時10分を指していた。退勤時間を思い返すと、ここに立ち始めて四十分は経っている計算になる。ほんの数分のつもりだったのに、時間だけが淡々と先へ歩いていってしまった。
腕はそろそろ文句を言い始めているのに、私はどこに置くべきか決められないまま、玄関に貼りついた影みたいに動けずにいた。いつもならただ通り過ぎるだけの玄関が、今日は急に“仕分け場”みたいになっていた。カバンを置く場所が「セーフ」なのか「アウト」なのか、たったそれだけの判定がどうしても下せない。
少し下ろすだけで終わるはずなのに、頭の中では「本当に大丈夫?」「あとで後悔しない?」という声が次々立ち上がり、思考のスペースはすぐ満席になる。そんなふうに堂々巡りをしていると、カバンの持ち手が汗でほんの少し滑った。そのわずかな感触が、胸の奥をチリッと刺激する。
置きたい私と、置きたくない私。どちらの言い分も分かるから、なおさら面倒くさい。そのどちらも“私”であることが、一番面倒くさい。
相変わらず立ち尽くしたまま、ふと足元の玄関マットに目をやる。昨日きれいに洗って乾かしたばかりで、私の中では“触れてはいけないほど清らかなマット”になっている。その清らかなマットが、まるで「汚れたカバンを持ったまま、ここから先へ進んでいいの?」と、ひそかに試してくるような気がした。
一歩踏み込んだ瞬間、その“清らかさ”を自分が汚してしまう気がして足が止まる。「本当に通っていいの?」声にならない問いだけが、静かに胸の奥に溜まっていく。判断の重さだけが、じわじわと肩にのしかかってくる。
玄関には小さな観葉植物も置いてある。「緑があると気分が落ち着く」と聞いて迎え入れたはずなのに、いまこの状況で言わせてもらうと、まったく落ち着かない。
むしろ葉っぱの裏に何かついていそうで、そっと距離を取ってしまう。癒しのはずのものまで、不安の種に変わってしまう。こういうところが、ほんとうにやっかいだ。
ラグも植物も、置く場所さえも、みんなが私の“判断待ち”をしているみたいで、静まり返った玄関の空気だけがどんどん重くなっていく。
私は静かな玄関で、カバンの重みと自分の判断力のなさを抱えたままひたすら立ち尽くしていた。体は疲れているくせに、頭だけはフル回転で、不安材料を自ら積極的に探し回っている。もう笑うしかない。こんな状況、誰が想像しただろう。帰宅して「ただカバンを置く」だけで、ここまでの大仕事になるなんて。
だって、たかがカバンだ。この部屋の誰よりも無害な存在のはずなのに、私はそのカバンに支配されている気がしてしまう。そう思うと辛いのと同時に可笑しくて、ついふふふと笑ってしまう。でも、その笑いはやはりどこか乾いている。
ガタンと外の音がした。隣の部屋の住人が帰ってきた音だ。その人はきっと、今カバンを床に置いた。何のためらいもなく、何の物語もなく。私は必死に「置くかどうか」で戦っているのに、その人は、たぶん何も考えずに置く。きっと明日の朝も、その人は何も気にせずカバンを手に取って出かけていく。
私はといえば、その“手に取る”までに、いちいち立ち止まってしまう——頭の中の不安材料を、ひとつずつ潰して、ようやく出発できるのだ。
こんなことを考えながらも私はまだ、カバンを持ったまま立っている。夜ごはんのことなんてすっかり頭にない。玄関灯の白い光がカバンの影を長く伸ばし、私の迷いを床いっぱいに映している。その影を眺めていると、さらに笑えてくる。——少しだけ笑える余裕は生まれたのに、それでも、どうするかだけは決められない。
———玄関で固まっていたあの時間を、いまもたまに思い返すことがある。あのときの私は、とにかく必死だった。世界の輪郭が少し遠くにぼやけて、カバンも玄関マットも、自分の心でさえも、どう関わればいいのかわからなくなっていた。動けなくて、決められなくて、ただ立ち尽くすしかなかったあの姿を、いまの私は、少しだけ距離をあけて眺めている。
あのときは見えなかったけれど、たぶんあの時間も、ちゃんと私の一部だった。