強迫性障害の人に、なんて声をかけたらいいんだろう?
やめたいのにやめられない——そんな葛藤のなかで苦しむ姿を見て、「自分にできることは何か」「どんな接し方が正解なのか」と悩んでいませんか?
強迫性障害(OCD)は、本人もつらいですが、支える側にとっても戸惑いの多い病気です。
善意でかけた一言が、思いとは逆に、不安を強めてしまうことも少なくありません。
だからこそ、強迫性障害の人にかける言葉でいちばん大切なのは、「正しいこと」を言うことより、「この人は、わかろうとしてくれている」と伝わること。その安心感があるだけで、当事者は「ひとりじゃない」と思える瞬間があります。
この記事では、強迫性障害の当事者が「かけてもらって救われた言葉」「逆につらかった言葉」の実例をもとに、安心感を与える声かけのヒントをまとめました。
家族、恋人、友人、職場の同僚——あなたのその思いやりが、相手の心を少し軽くするきっかけになります。
 ぴょんた
ぴょんたなんて声をかけたらいいか、本当に迷うよね…。
 よたきち
よたきちこの記事で“寄り添い方”を一緒に見つけていこう。
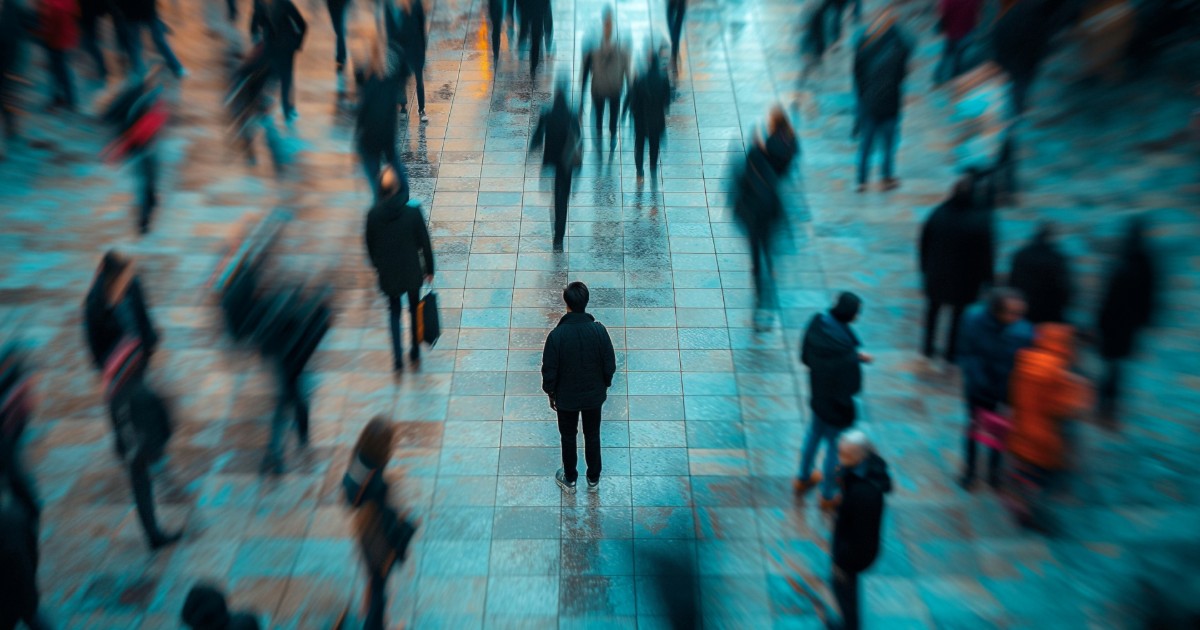
- 強迫性障害の人への声掛けに悩んでいる
- 励ましが逆効果にならないか心配
- 正しい接し方がわからず戸惑っている
強迫性障害の人にかける言葉が難しい理由

強迫性障害の人が「やめたいのに、やめられない」と苦しんでいるのは、単なる気の持ちようや性格のせいではありません。
実は、脳の働きそのものに関係しているということが、近年の研究でわかってきています。
とくに関係しているのが、「前頭前野」や「基底核(尾状核)」と呼ばれる部分。
これらは「気持ちを切り替える」「不安を調整する」働きを担っていますが、強迫性障害ではこの回路がうまく働かず、同じ考えが頭から離れなくなったり、不安が強くなりすぎてしまうのです。
さらに、セロトニンやドーパミンといった脳内の伝達物質のバランスも崩れがちで、「強迫行為をすると不安がやわらぐ」という誤った学習が脳内で強化されてしまいます。
つまり、本人の中では「やらないと不安でたまらない」という信号が、本物の危険のように働いてしまうのです。
外から見ると「大げさ」に見える不安も、本人の中では、まるで火災報知器が鳴りっぱなしのような状態です。止めたくても止められないのは、気持ちの弱さではなく、脳がずっと非常ベルを鳴らし続けているから。
それほど切迫した感覚の中で、毎日を過ごしているのです。
そのため、治療では「不安を感じても、行動を変えてみる」練習(曝露反応妨害法:ERP)を通じて、「やらなくても大丈夫だった」という新しい学習を脳に伝えていくことが大切になります。
こうした背景を知ることで、「気にしすぎだよ」「そんなこと考えなくてもいいじゃない」といった言葉が、どれほど本人を追い詰めてしまうかが、少しずつ見えてくるはずです。
だからこそ、まずは「この人にとっては、本当に耐えがたい不安なんだ」と理解すること。
大切なのは「正しい言葉」よりも「理解しようとする姿勢」です。その姿勢が伝わるだけで、当事者にとっては大きな支えになります。

なぜ「言葉のかけ方」が大切なのか

強迫性障害のある人は、自分の思考や行動を「おかしい」と分かっていても止められない苦しみを抱えています。その裏には、罪悪感や恥ずかしさ、周囲に理解されない孤独感が重なっていることも少なくありません。
そんなとき、何気ない一言が心を軽くすることもあれば、逆に深く傷つけることもあります。
「なんでそんなこと気にするの?」と否定されれば、孤立感や自己否定感が強まりますが、「つらいよね」「わかるよ」と受け止められれば、張りつめた心がふっと緩むこともあります。
つまり、言葉は“症状を治す道具”ではなく、“安心できる関係をつくるきっかけ”です。
大切なのは、相手を変えようとする言葉ではなく、「理解しようとしている」という気持ちが伝わる言葉。たとえ短いひと言でも、その温度が相手の安心につながります。
本人が求めているのは「正解」ではなく「安心感」

強迫性障害の人が何度も「鍵を閉めたかな?」と気にしているとき、つい「ちゃんと閉めたよ」と答えて安心させたくなるかもしれません。けれど、その答えは一時的な安心にはつながっても、「また確認しなければ落ち着けない」という悪循環を強めてしまうことがあります。
実際に本人が欲しているのは、“正しい答え”ではなく“不安を受け止めてもらえる感覚”です。
「本当は閉めたって分かっているのに、不安が消えないんだね」と、その気持ちに寄り添うだけで、孤独の中にいる本人に「理解してもらえた」という安心が生まれます。
言葉で症状を止めることはできません。けれど「その気持ちは大切にしていいよ」「安心できなくてつらいよね」といった共感の言葉は、不安に振り回される心を落ち着ける小さな支えになります。
本人に必要なのは、正解を突きつけることではなく、「不安を抱えていても受け入れてもらえる」という確かな手ごたえなのです。
強迫性障害の人に安心をあたえる言葉

強迫性障害の人に本当に必要なのは、不安を消してくれる言葉ではありません。その不安がどれだけ苦しいかを、わかろうとしてくれる言葉です。
「大丈夫」「気にしすぎだよ」といった言葉は、励ましのつもりでも、不安そのものを軽く扱われたように感じさせてしまうことがあります。
だからこそ大切なのは、不安をなくそうとすることではなく、その不安に振り回されている自分のつらさを、否定せずに受け止めてもらえる感覚を届けること。
ここから紹介するのは、そんな“安心につながる言葉”たちです。
「大丈夫、一緒に乗り越えよう」
強迫性障害の人は、不安を抱えるなかで孤独感を感じやすいものです。「一人じゃないよ」「一緒に乗り越えよう」というメッセージには、精神的な負担をやわらげる力があります。
とくに「大丈夫」という言葉は、相手の不安に共感しつつ、安心感を与える効果があります。押しつけがましくなく、寄り添う気持ちを込めて伝えることが大切です。
「無理にやめなくても大丈夫。焦らず少しずつ進もう」
強迫行為を無理にやめさせようとすると、不安やストレスが強まり、かえって症状が悪化することがあります。認知行動療法では、不安を「なくす」ことよりも、不安に過剰に反応しない練習が重視されます。
だからこそ、「焦らなくていいよ」「ゆっくりで大丈夫」という言葉は、プレッシャーを取り除き、安心して回復に向き合える環境を作る手助けになります。
「つらかったね。でも、少しずつ良くなっているよ」
強迫性障害の改善には時間がかかるものです。だからこそ、小さな変化や努力に気づいてあげることが、本人の自信や希望につながります。
「前より少し笑顔が増えたね」「この前は不安を乗り越えられてたね」といった言葉も、前進を実感させるうえでとても大きな意味を持ちます。回復のペースを尊重し、前向きなフィードバックを伝えていきましょう。
「話してくれてありがとう」
苦しい気持ちを口にすること自体が当事者にとって大きなハードルです。その一歩を肯定してくれる言葉は、信頼関係を深めます。

強迫性障害の人を傷つけるNGワード

「気にしすぎだよ」
強迫観念は、「気にしないようにしよう」と意志で抑えられるものではありません。むしろ、抑えようとするほど頭から離れなくなるという特徴があります(思考抑制の逆説的効果:Wegner et al., 1987)。このような言葉は、「症状への理解がない」と患者に感じさせ、孤立感を深める原因になります。
「何でそんなことをするの?」
行動の理由を問われても、本人が納得のいく説明をするのは難しいことがほとんどです。このような問いかけは、患者に「理解されていない」と感じさせ、不安や自己否定感を強めてしまう可能性があります。
「なぜやめられないの?」
強迫行為には、時に「やめたら何か悪いことが起きるかもしれない」といった切迫感が伴います。この問いは、苦しみを十分に理解されていないと感じさせ、孤立感や罪悪感を深めることがあります。
支える側も、自分を責めないことが大切
強迫性障害のある人を支えることは、思っている以上にエネルギーを使います。
「正しく対応しなければ」「傷つけないようにしなければ」と力が入りすぎると、今度は支える側が疲れ果ててしまい、関係そのものがぎくしゃくすることもあります。
大切なのは、“完璧な対応”を目指さないことです。うまく言葉をかけられなかったり、ついイライラしてしまったりしても、それは自然なこと。寄り添いたいと思う気持ちがあるだけで、相手には十分に伝わっています。
そして、自分を守る工夫も忘れてはいけません。
- 一人で抱え込まず、専門家に相談する
- 家族会やピアサポートなど、同じ立場の人とつながる
- ほんの短い時間でもいいから、自分の休息を大切にする
これらは、支え続けるための大切な土台です。自分の余裕を保つことが、結果的に相手を支える力にもつながります。
支える側が無理を重ねてしまうと、心にも体にも負担がたまり、関係そのものがしんどくなってしまうことがあります。だからこそ、自分を大切にすることは、相手を大切にすることと同じくらい大事なことなのです。
職場で私がどんな“強迫症状”と向き合っていたのか。今では少し笑えるけれど、当時は必死でした。
よたきちの実話エッセイ『七階までのボタン戦争』はこちら

まとめ
強迫性障害と向き合うのは、本人にとっても、そばにいるあなたにとっても簡単なことではありません。
「これで合っているのかな」「余計なことを言ってしまったかも」――そんな迷いを抱きながらも支えようとする気持ちこそが、何よりの力になります。
大切なのは、完璧な言葉を探すことではなく、「不安を否定せず、安心につながるかどうか」で言葉を選ぶこと。
その基準さえあれば、迷ったときも自然と“正しい寄り添い方”に近づけます。
言葉が見つからないときは、無理に話さなくても大丈夫です。黙ってそばにいることもまた、安心のかたちのひとつです。
支える側が疲れをためすぎないよう、自分の休息も大切にしながら、少しずつ一緒に歩んでいきましょう。
そして、もっと具体的に知識や工夫を得たいと思ったら、こちらの記事を参考にしてみてください。私自身が助けられた本をまとめています。
→ 【読んでよかった!不安な毎日に“役立った”強迫性障害の本5選】





