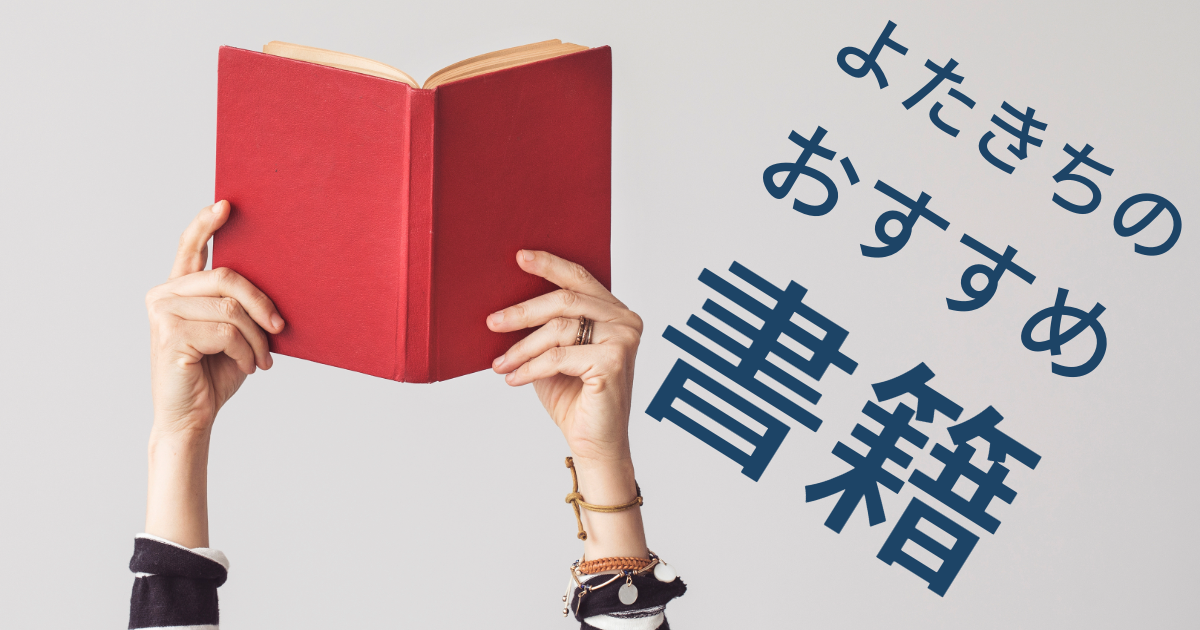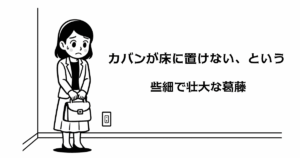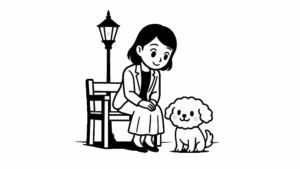強迫性障害と過ごしてきた時間の中から、今も時折思い出すワンシーンを綴っています。
私の職場は、大学病院に隣接する医学部の建物の七階にある。
“医学部”という単語の持ついかにも重々しい感じと、“七階”という数字が示す地味な高さ。
その二つが合わさると、当時の私には、毎日そこへ向かうだけでなぜかハードモードのステージに挑まされているように思えた。
そして実際、地獄だった。
毎朝出勤するたびに私は、七階にたどり着くまでの“ボタン問題”に立ち向かわなければならなかったのだ。
医学部のエレベーターは意外と混む。研修医、医学生、教授、研究員、業者、そして——私。人の出入りが激しいうえに、医学部内という場所柄、誰がどんな菌を持っているかもわからない(と、当時の私は本気で思っていた)。そして、その不安の中心にあるのが「ボタン」だった。誰もが触り、誰もが気にしていない。つまり、“人類の共有部分”。私の敵は、毎朝そこにいた。
当時の私は、ボールペンでボタンを押していた。持ち手の反対側、キャップの部分で、できるだけ垂直に、無駄なく。指先が触れないように呼吸まで止めて、ボタンのランプが点くまでの一秒間に全神経を集中させる。ボールペンの芯に触れた“何か”が私の手に伝わらないよう、体中のセンサーを総動員していた。まるで手術中の執刀医のような集中力。それが、私の毎朝の儀式だった。
ただ、この作戦には一つ欠点があった。——人がいると、できない。
ある朝、私はいつものように誰もいないエレベーターに乗り込み、ポケットからボールペンを抜いた。すると、扉が閉まる直前に後ろから研修医らしき男性が「すみません」と言って乗り込んできた。その瞬間、私の体はフリーズした。フェンシングのような体勢でボールペンを握ったまま固まる女。相手は訝しげな目で私を見る。仕方なく、私は自然を装ってペン先を戻し、何事もなかったかのように指で押した。だが内心では、“汚染”の音が聞こえていた。ジュッ——精神的に指先が焼け焦げるような感覚。それでも笑顔をつくり、「おはようございます」と言う。こんな状況でも笑顔を保てる社会人としての演技力は、もはやプロの域だ。
だがプロには常に“次の一手”が必要だ。
ボールペン作戦が封じられたときのために、私は“フェイント押し”という秘技を編み出していた。
たとえば、誰かが降りる瞬間、ドアの「開」ボタンのすぐ横に手を伸ばし、指先をほんの少し浮かせたまま、第二関節でボタンを“かすめる”。
指はボタンに触れていない。たぶん。いや、触れていないと信じたい。
外から見れば、親切に「開」ボタンを押し、ただドアの開いた状態を支えているようにしか見えない——完璧なカモフラージュ。
自分でも笑うほど無意味に洗練された動きで、「今日もボタンとの接触を避けられた」と心の中で小さくガッツポーズを取った。
もちろん、失敗も多かった。
とくに厄介なのは、誰かが途中の階から乗り込んできて「五階お願いします」と言う瞬間だ。
あれは、私にとっての“想定外イベント”の代表格だった。
「五階ですね」と、社会人としての礼儀をぎりぎりの笑顔で返しながら、心の中では別の声が暴走していた。
――なぜ乗ってきた、なぜ私に頼むんだ、自分で押してくれ!今ので計画が崩れた!
ボタン一つで崩壊するその“計画”は、私にしか見えていない世界のルールだった。
たとえば、「今日は自分の指ではボタンを押さないで出勤を終える」という密かなミッション。
あるいは、「このボールペンでしか触らない」という潔癖な誓い。
そんな、誰に説明しても苦笑いされるようなルールを、自分の中だけで真剣に守っている。
だから、見知らぬ誰かの「五階お願いします」は、私にとってはもはや“平和な顔をしたテロ行為”に近い。
しかし、ボタンを押さないわけにはいかない。人としての体裁がある。
結局、私は心の中で小さく「ぎゃー」と叫びながら、ためらいがちに指を伸ばす。
そしてその瞬間、頭の中でカウントが始まる。
――今、触った。今ので指が“アウト”になった。すぐに洗面所でリセットしなければ。
人にとってはたった数秒のたわいのない出来事なのに、私の一日はそこで小さく分岐する。
「触った手で何を触るか」「どのタイミングで洗うか」。
頭の中のマップが、最新の感染ルート図のように書き換えられていく。
そんな生活を続けていたら、いつのまにか私は、エレベーターの“偵察兵”になっていた。
扉の前で人の気配をうかがい、足音がすればさりげなく靴紐を結ぶフリ。
誰もいなければミッション成功、静かな上昇開始。
途中で誰かが乗り込んでこないように、心の中では「頼む、次の階では誰もいませんように」と、もはや祈祷レベルの願掛けをしていた。
誰かが待っていれば……潔く一本見送る。自分でも笑えるほど慎重な防衛戦だった。
そんな戦いが続くうちに、私はある朝、突然ひらめいた。「階段で行けばいいんじゃないか、七階まで。」
エレベーターを避ければ、ボタンに触れる必要がない。
その発想が妙に清々しく思えて、私は久しぶりに勝利の予感を感じた。
朝一番の寝ぼけた体にムチを打ち、私は勇気を出して階段を上り始めた。一階、二階、三階。まだ余裕。四階あたりで息が切れ、五階で尋常じゃない汗がじっとりしてくる。六階で足が震え、手すりにしがみつきたい衝動にかられた。けれど、ボタンを避けたいがために階段という手段を選んだこの私が、手すりにしがみつくわけにはいかない。
手すりもまた、“不特定多数の指先ゾーン”なのだから。
そして七階に着くころには、心拍数がボタン問題をはるかに超えていた。「結局、私を倒すのは菌じゃなくて階段か……」。結局その翌日、私はまたボールペンをポケットに入れて出勤した。
こうして、私の“ボタン戦争”は連日続いた。ボールペンの持ち方にも独自のルールが生まれた。右手でペンを出し、押した後はキャップを左手で受け取り、ペン先を内側にしまってポケットへ。その一連の動作には0.3秒のズレも許されなかった。完全に儀式だった。ボタンを押すたび、私は小さな祈りを捧げていた。
今ではもう、ボールペンを使わない。素手で押す。だが、押した瞬間のあの「ピリッ」とした感覚は、まだ指のどこかに残っている。
思えばあの頃の私は、汚れを避けていたというより、“過剰に反応してしまう感覚”と戦っていたのだと思う。
医学部の建物だから、薬品や検体に触れた手でボタンを押す人もいる。だから、完全に清潔とは言えない。けれど、私の恐れはそこから何倍も膨らんでいた。
「ちょっと嫌だな」が、いつのまにか「触ったら終わり」に変わっていく。理屈ではなく、感覚の方が先に世界を決めてしまうのだ。そうしてボタン一つが、毎朝の“生きるか死ぬか”の境界線になる。
その恐怖の境界だと信じていたものが、ただのボタンに過ぎないと受け入れられるようになったころには、私のポケットから、ボールペンがいつのまにか消えていた。
いまでも、朝エレベーターの前に立つと、ついポケットを探してしまう。もうボールペンは入っていないのに。エレベーターの鏡越しに、昔の自分と目が合う気がする。そのたびに、私は軽く息をついて、指でボタンを押す。けれど、あの頃より少しだけ静かな気持ちで、七階に向かえる。
一人暮らしを始めてから、強迫性障害の症状が少しずつ悪化していった頃。
あの頃の私を支えてくれたのは、ほんの数冊の本でした。
不安な毎日と向き合う決意をしたときに、きっとヒントになると思います。
『読んでよかった!不安な毎日に“役立った”強迫性障害の本5選』はこちら