「なんだか気にしすぎる人だな」と思っていた部下や同僚が、ある日「強迫性障害と診断されました」と打ち明けてきた。そんな場面に直面したとき、多くの人は、どう反応すればいいのか分からなくなります。
「支援したい。でも、どう関わればいいかわからない…」
「特別扱いしすぎるのも違う気がする…」
「どこまで配慮すればいいのか見当がつかない…」
――そう感じるのは、すごく自然なことです。
強迫性障害への対応に、「これが正解」という万能な答えはありません。優しい言葉をかければ解決するわけでも、すべての不安に合わせて環境を変えればいいわけでもない。
大切なのは、無理に支えようとしすぎないこと。不安をゼロにしようとしないこと。そして、仕事が回るラインを一緒に守ること。
この記事では、戸惑っている上司や同僚の立場から、「やりすぎない、現実的な支援の形」を整理していきます。
 よたきち
よたきち気持ちだけで抱えず、業務が回る形を先に整える。その視点で一緒に整理していきます。
 ぴょんた
ぴょんた一緒に学ぼう!
- 強迫性障害の部下や同僚がいて、接し方に悩んでいる方
- 配慮したい気持ちはあるけれど、何をすればいいのか分からない方
- 精神疾患への対応に不安を感じている上司・人事・管理職の方
- 「支援」と「特別扱い」の違いに戸惑っている方
強迫性障害(OCD)とは?
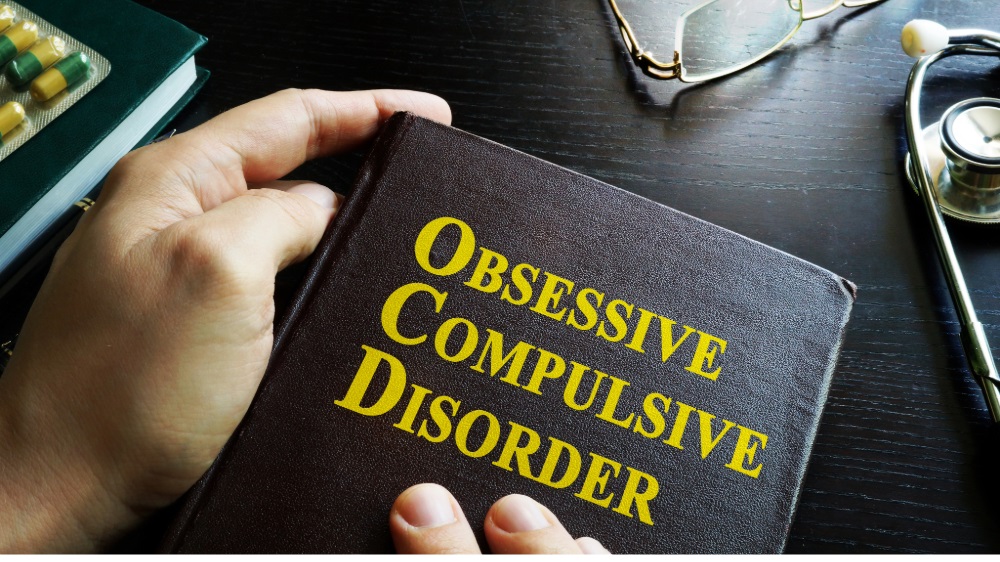
強迫性障害(OCD)は、「頭では不合理と分かっていても、不安を打ち消すために、やめたくてもやめられない行動を繰り返してしまう」病気です。
職場では、次のような行動として表れることがあります。
こうした行動は、「几帳面な性格」や「こだわり」と見なされがちですが、実際には不安を和らげるために本人が必死で行っている対処行動です。
本人自身も、「やめたいのにやめられない」ことで大きなストレスを抱え、日々葛藤しています。
強迫性障害について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
職場で求められる支援の考え方とは?

“共感”よりも“仕組みと理解”
職場で求められるのは、「気持ちに寄り添うこと」だけではありません。大切なのは、どうすればお互いに働きやすくなるかを考える姿勢です。強迫性障害のある人は、自分でも「おかしい」と分かっていても、強い不安のために行動をやめられないことがあります。だからこそ、つらさに共感する言葉をかけること自体は、とても大切です。
ただ、ここでひとつ、誤解されやすいポイントがあります。
支援という言葉は、ときに「何でもしてあげること」みたいに受け取られがちです。でも、強迫性障害の支援で本当に大切なのは、「不安を減らしてあげること」ではなく、「不安があっても現実が回る状態を一緒につくること」です。
気持ちは受け止める。理解は示す。でも、不安そのものには付き合いすぎない。
この線引きがないと、善意の支援が、かえって症状を長引かせてしまうこともあります。
だからこそ、「不安があっても業務をこなせる」「不安になっても対応しやすい」そんな“仕組み”を整えることが、現実的で長く続く支援につながります。

職場でできる5つの対応

強迫性障害を抱える人にとって、職場での働きやすさは「不安を感じないこと」よりも、「不安があっても業務を続けられる仕組み」があるかどうかで大きく左右されます。
厚労省資料に示される合理的配慮の一般的な考え方を参考にしながら、強迫性障害で起きやすい困りごとに対して“業務が回る形”を優先した工夫を整理します。
対応例①:「曖昧な指示を避け、ゴールを明確に」
強迫性障害では、「失敗したら取り返しがつかないかもしれない」という不安から、確認作業を繰り返してしまい、作業に時間がかかることがあります。とくに「どこまでやればOKか」が曖昧なままだと、合格ラインを探し続ける形になり、確認が止まりにくくなります。
厚生労働省の「障害別にみた特徴と雇用上の配慮」では、精神障害のある人に対しての配慮の例として、業務や指示の運用を調整するという考え方が提示されています。
これらは特定の疾患に限定した指針ではありませんが、「業務が止まらないための条件を、先に整えておく」という考え方は、強迫性障害の職場支援にも応用できます。とくに強迫性障害では、「どこまでやればOKか」が曖昧だと、不安から確認ややり直しが止まらなくなりやすいため、完了条件をあらかじめ具体化しておくことは、運用としてかなり合理的です。
ゴールが明確になるほど、「ここまでで提出していい」という判断がしやすくなり、確認を増やしにくくなります。これは、本人の気持ちを楽にするためというよりも、業務を止めないための現実的な工夫です。
- 完成条件:
(例)誤字チェックは1回まで/数値はこの2項目だけ再確認/体裁は社内フォーマット準拠 - 優先順位:
(例)納期が最優先/正確性が特に重要なのはこの項目だけ - 締切:
(例)一次締切は○時、最終締切は○時(「ここで出す」を先に合意) - ここから先は上司判断:
(例)迷ったら10分で相談。以降は上司がOKを出したら提出
これは「何度も確認してもいいよ」という配慮ではありません。むしろ、確認が増えないようにするための設計です。
合格ラインが曖昧だと、不安が強いほど「どこまでもやり直せる状態」になってしまいます。だからこそ、先に区切りを作っておくことが、不安に付き合いすぎず、業務を回し続けるための支援になります。
対応例②:衛生へのこだわりに理解を示す
強迫性障害の中には、汚れや菌、他人との接触に対して、強い恐怖や不安を感じるタイプがあります。
職場では、共用のマウスやキーボード、書類の受け渡し、ドアノブや備品の使用など、日常的な場面が大きなストレス源になることもあります。
本人にとっては、「気にしすぎ」ではなく、強い不安が自動的に湧き上がってくる感覚に近く、それを打ち消すために避けたり、拭いたり、手洗いを繰り返したりせざるを得ない状態です。
厚生労働省の「障害別にみた特徴と雇用上の配慮」では、精神障害のある人に対する配慮の一例として、環境への過敏さやストレス要因に配慮し、作業環境や業務の進め方を調整することが挙げられています。
これは特定の症状を想定したものではありませんが、強迫性障害で衛生や汚染への不安が強い場合にも、「業務を止めないための条件調整」という発想として応用できます。
たとえば、次のような調整が考えられます。
- パソコンのマウスやキーボードを個人専用にする
- 文房具を共用にせず、本人専用のものを用意する
- 書類の受け渡しを、手渡しではなく机の上で行う
といった小さな調整だけでも、不安が強く出る場面を減らすことができます。
こうした配慮は、「不安を完全に取り除くこと」が目的ではありません。
あくまで、業務を止めずに進めるための条件を整えることが目的です。
衛生面の配慮をするかどうか迷ったときは、次の観点で整理すると、「やりすぎ」や「支援不足」のどちらにも寄りにくくなります。
- それがないと業務が止まるか?→ ないと作業に入れない・極端に時間がかかる場合は、必要最小限の配慮として検討価値あり。
- それは「業務上の要件」か、「安心のための上乗せ」か?→ 安心のためだけの上乗せ要求が広がりすぎていないかを確認する。
- 安全・衛生・品質に関わるか?→ 会社全体のルールや安全基準と矛盾していないか。
- チームや業務全体への負担は過大ではないか?→ コスト・手間・他の社員の不公平感が大きくならないか。
すべての不安要因を取り除こうとすると、かえって「この条件がないと働けない」という形で症状を固定化してしまうこともあります。
だからこそ、「業務に支障が出ないための最低限の調整」と「不安そのものを消すための調整」を、意識的に分けて考えることが大切です。
不安に寄り添う姿勢は大切ですが、不安そのものに付き合いすぎない線引きが、結果的に本人の回復や自立を支えることにもつながります。
対応例③:「勤務場所や時間帯の柔軟な調整」
強迫性障害のある人の中には、特定の環境に強い不安や不快感を覚えやすいタイプがあります。
- 人の出入りが多い場所
- 周囲の視線を強く感じる席
- 騒音や物音が多い環境
- 背後を人が通るレイアウト
などでは、常に緊張状態になり、不安や強迫症状が強く出てしまうことがあります。
その結果、作業に集中できなくなったり、確認ややり直しが増えたりして、業務効率が大きく落ちてしまうケースも少なくありません。
厚生労働省のメンタルヘルス対策関連資料では、メンタルヘルス不調のある人に対して、作業環境や業務条件を調整することが支援策の一つとして示されています。これは「不安をなくすこと」を目的にしたものではなく、業務が継続できる条件を整えるという意味合いに近い考え方です。
強迫性障害の場合も、この発想を応用して、不安が強く出やすい環境要因を減らすことで、不安があっても業務を続けられる状態に近づける、という位置づけで考えるのが現実的です。
たとえば、次のような調整が考えられます。
- 人の往来が少ない席への配置換え
- 背後に人が立ちにくいレイアウトへの変更
- 比較的静かな場所での作業
- 一部業務のみ、個室や会議室で行う
- 混雑を避けた時差出勤
- テレワークと出社の併用(可能な範囲で)
こうした工夫によって、「不安があると仕事が止まる」状態から、「不安があっても仕事は続けられる」状態に近づけることができます。
勤務場所や時間帯の調整をするか迷ったときは、次の観点で整理すると、独断的な配慮や、やりすぎを防ぎやすくなります。
- その環境要因が原因で、業務が明らかに止まっているか?→ 不安や症状のせいで、作業が極端に遅れている・進まない場合は検討価値あり。
- 調整しない場合、本人のパフォーマンスが大きく落ちるか?→ 成果物の質・納期・集中力への影響が出ていないか。
- チームや業務全体への影響は過大ではないか?→ 他の社員の負担が増えすぎないか、業務が回らなくならないか。
- 一時的な調整として試せるか?→ まずは「試行期間」を決めて様子を見る、という形も有効。
ここで大切なのは、「不安を感じない環境を用意すること」そのものが目的ではない、という点です。あくまで目的は、不安があっても、業務が現実的に回る状態をつくること。
そのために、業務に支障のない範囲で環境を調整する、というスタンスが、長く続く支援につながります。
対応例④:情報共有は最小限に(※本人の同意を前提に)
強迫性障害をはじめとする精神疾患に関する情報は、職場の中でもとくに慎重に扱う必要があります。
本人が打ち明けてくれた内容は、それ自体が大きな勇気のいる行為であり、「仕事を続けたい」「理解してほしい」という切実な思いが込められていることも少なくありません。だからこそ、善意であっても、本人の許可なく病名や症状を周囲に共有することは、強い不信感や不安を生み、結果的に支援そのものを難しくしてしまうことがあります。
厚生労働省のメンタルヘルス対策に関する資料では、健康情報の取り扱いについて、本人の同意を前提に、目的を限定し、必要最小限の範囲で扱うことの重要性が示されています。
これは強迫性障害に限った指針ではありませんが、職場で疾患情報を扱うときの基本原則として、強迫性障害の支援場面でもそのまま参考にできる考え方です。
周囲に配慮内容を伝える必要がある場合でも、共有すべきなのは「病名」ではなく、業務上必要な配慮の内容です。
たとえば、次のような伝え方が考えられます。
- 「体調管理のため、特定の業務について進め方を調整しています」
- 「集中しやすい環境を整えるため、席の配置を一部変更しています」
- 「業務効率の観点から、確認フローを簡略化しています」
このように、配慮の理由を必要以上に説明せず、業務上の運用として淡々と共有することで、周囲の理解を得ながら、本人のプライバシーも守ることができます。
情報をどこまで共有するか迷ったときは、次の観点で整理すると、支援が破綻しにくくなります。
- 本人の明確な同意があるか?→ どこまで、誰に、何を伝えるかを事前に合意しているか。
- それは業務上、本当に必要な情報か?→ 単なる説明用・雑談用の情報になっていないか。
- 病名や症状の詳細である必要があるか?→ 配慮内容だけでは足りないのかを検討する。
- 共有範囲は最小限に絞れているか?→ 直属の上司や関係者だけで足りないか。
ここで大切なのは、「周囲の納得を得るために、本人の個人情報を差し出す」という構図をつくらないことです。
配慮は、あくまで業務を円滑に進めるための調整であり、本人が説明責任を負う存在になる必要はありません。本人の同意を尊重し、必要最小限の情報だけを、必要な範囲に共有する。この線引きを守ることが、
結果的に、本人の安心感を守り、職場での支援を長く続ける土台になります。
対応例⑤:否定せず、安心感を与える声かけを
強迫性障害のある人にとって、「気にしすぎだよ」「大丈夫だから」「もう確認したでしょ」といった言葉は、本人が一番言われたくない言葉でもあります。
本人自身も、「気にしすぎだ」と頭では分かっていて、それでも不安が止まらず、苦しんでいるからです。だからこそ、不安やつらさそのものを否定しない姿勢は、とても大切です。
一方で、ここには強迫性障害特有の落とし穴もあります。
上司や同僚が善意で、
- 「大丈夫だよ、ちゃんとできてるよ」
- 「私が確認したから平気だよ」
- 「何も問題ないって保証するよ」
といった言葉を何度もかけてしまうと、それ自体が“安心をもらうための行動”になり、結果的に、強迫症状を長引かせてしまうことがあります。
いわゆる「巻き込み」や「安心の代行」に近い状態です。
ここで大切なのは、不安を消してあげる声かけではなく、不安があっても仕事を前に進められる声かけに切り替えることです。
たとえば、次のような言い方が考えられます。
- 「不安なのは分かった。今の手順どおり、ここまでで一度区切ろう」
- 「気になるのは自然だよ。その上で、締切どおりこの形で出そう」
- 「迷ってるのは伝わってる。10分考えて、それ以上は一緒に止めよう」
- 「ここから先は私がOKを出すから、いったん提出しよう」
厚生労働省のメンタルヘルス対策関連資料では、本人の感情や状態を否定せず、困っていることがあれば相談できる関係性をつくることの重要性が示されています。
ただし、強迫性障害の場合は、「不安を打ち消すための声かけ」がかえって症状を長引かせてしまうこともあるため、共感と同時に“業務を前に進める線引き”を入れることが、実務上とても重要になります。
- その声かけは「安心の保証」になっていないか?→ 「大丈夫」「問題ない」の連発になっていないか。
- その声かけは「確認の代行」になっていないか?→ 上司が代わりに何度も確認していないか。
- その声かけは「行動を前に進める内容」になっているか?→ 区切り・締切・次の一歩が含まれているか。
ここで目指したいのは、優しいけど、ブレーキもある関わり方です。
不安やつらさには共感する。でも、不安そのものの解消役にはならない。
その代わり、「不安があっても業務を終えられる形」を一緒につくる。
それが、強迫性障害のある人にとっても、職場にとっても、現実的で長く続く支援になります。

「公平性」と「支援」のバランスをどうとる?

「配慮をすると他の人が不公平に感じるのでは…」
そんな声は、職場で支援を考えるときによく挙がる疑問です。確かに、一部の社員にだけ特別な対応をしているように見えると、他の社員からの反発や誤解を招くこともあります。
しかし、ここで大切なのは「支援=特別扱い」ではないという視点です。
厚生労働省が示す「合理的配慮」とは、その人が力を発揮できるように、必要な条件や環境を整えることを意味します。
たとえば、車いすを利用する社員のためにスロープや昇降機を設置することは、“特別扱い”ではなく、業務を円滑に進めるための正当な環境整備です。
それと同じように、強迫性障害を抱える人にとっての「静かな作業環境」や「明確な業務指示」があることは、仕事の質を保つために必要な条件であり、“特別扱い”ではありません。
むしろ支援のあり方を正しく共有することで、周囲の理解が深まり、職場全体の安心感や働きやすさが高まります。
強迫性障害に限らず、「個別に配慮する文化」が根付くことは、誰かが困ったときに自然と手を差し伸べられるチームづくりにもつながります。
まとめ:一緒に働き続けるためにできること
強迫性障害の本質は、几帳面な性格ではなく、「不安を和らげるための行動が、自分の意思ではやめられない病気」であるということです。
だからこそ、曖昧な業務指示を避け、安心して働ける環境を整えることが、支援の第一歩となります。
無理に変えようとするのではなく、「今できること」を一緒に探しながら進んでいく——そんな関わり方が、本人の安心感を支えるだけでなく、周囲との信頼関係を育て、職場全体の土台を強くしていきます。
上司や同僚、それぞれができる配慮は、決して“特別扱い”ではなく、チームの成熟を促す大切な要素です。
明確な指示や安心できる仕組みは、強迫性障害のある人に限らず、誰にとっても働きやすさにつながり、結果として力を引き出すことにもなります。
本人の希望を尊重しながら、必要に応じて産業医や専門家と連携することも、有効な選択肢のひとつです。
強迫性障害のある人も、そうでない人も、誰もが安心して力を発揮できる職場をつくることは、組織全体にとって大きな価値となるはずです。




