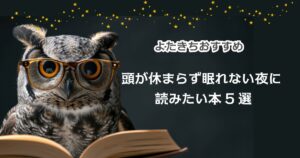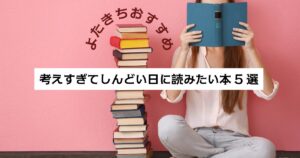「なんとなく気分が落ち込む」「不安を感じやすい」——そんなとき、食べるものを意識したことはありますか? 実は、特定の栄養素が脳に働きかけ、ストレスを和らげたり、気分を安定させたりする可能性があることが示されています。脳は日々の食事から得た栄養を使って神経伝達物質を作ったり、脳細胞を修復しています。
そのため、どんな栄養を摂るかによってメンタルの安定やストレスへの強さに影響を与える可能性があるのです。この記事では、不安を軽減し、心のバランスを整えるために役立つ栄養素と、それを多く含む食材を詳しくご紹介します。
 よたきち
よたきちメンタルに影響を与える可能性のある栄養素の中から、代表的なものをいくつかご紹介します。
 ぴょんた
ぴょんた食べて不安を吹っ飛ばそう!
- 不安や緊張を感じやすく、少しでも心を落ち着けたいと思っている
- 食べ物や栄養で気分を整える方法を探している
- 薬や治療以外にも、自分でできるケアに興味がある
- 気分の波に振り回されやすく、できることから改善したいと考えている

不安と食事の関係とは?
不安や気分の落ち込みは、心だけでなく、体や脳の状態とも深く関係しています。
その背景には、脳のはたらきや神経伝達物質のバランスが関わっており、それらを支えるのが、日々の食事からとる栄養素です。
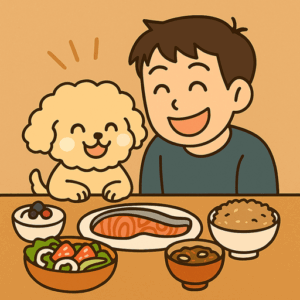
たとえば、「幸せホルモン」とも呼ばれるセロトニンは、脳内で気分の安定に関わる重要な物質ですが、
このセロトニンの材料になるのは、トリプトファンやビタミンB6といった栄養素です。
また、脳のストレス反応を抑える働きをするマグネシウムや、神経細胞の修復を助けるオメガ3脂肪酸なども、「脳の健康」や「心の回復」に欠かせない存在です。
つまり、どんな栄養をとるかは、“脳のはたらき方”そのものを左右する可能性があるのです。
これから紹介する栄養素の前に、まずはあなた自身の状態をセルフチェックしてみましょう。
当てはまる項目が多い栄養素から意識してみるのがおすすめです。
あなたに足りていない栄養素は?セルフチェックで確認
栄養の解説に入る前に、ご自身の状態を簡単に確認できるチェックリストを用意しました。以下の項目に当てはまるものが多い栄養素を、意識して補ってみましょう。
トリプトファンが不足しているかも?
トリプトファンは“幸せホルモン”セロトニンの材料。不足すると気分や睡眠に影響が出やすいといわれています。どんなサインがあるのか、セルフチェックしてみましょう。

□ 理由もなく不安になることがある
□ 眠れない・眠りが浅い
□ 気分の波が激しい
□ 甘いものや炭水化物を無性に食べたくなる
□ 集中力が続かず、考えがまとまりにくい
マグネシウムが不足しているかも?
マグネシウムは“体を整えるミネラル”と呼ばれ、筋肉や神経、エネルギー代謝に欠かせません。不足するとこむら返りや疲労感につながることがあります。どんなサインがあるのか、セルフチェックしてみましょう。

□ ストレスに弱く、イライラしやすい
□ 筋肉のこわばりやこむら返りが起こりやすい
□ 睡眠が浅い・寝つきが悪い
□ 頭痛や緊張性の肩こりがある
□ 甘いもの・カフェインがやめられない
オメガ3脂肪酸が不足しているかも?
オメガ3脂肪酸は、脳や心の働きを支える大切な脂質です。不足すると集中力や気分の安定に影響したり、炎症が起こりやすくなるといわれています。次のチェックリストで確認してみましょう。
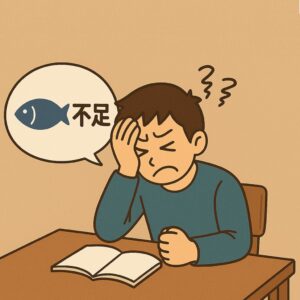
□ 肌や髪の乾燥が気になる
□ 集中力が続かず、頭がぼんやりする
□膝や関節に違和感や炎症を感じることがある
□夜ぐっすり眠れず、睡眠が浅い気がする
□疲れやすく常にだるい
□気分が落ち込みやすく不安定
ビタミンB群が不足しているかも?
ビタミンB群はエネルギーをつくり出し、心と体を元気に保つために欠かせない栄養素です。不足すると疲労感や口内炎、気分の落ち込みが出やすくなります。当てはまる症状がないか、チェックしてみましょう。

□ 疲れやすく、朝からだるい
□ 食欲がなく、気分も落ち込みがちになる
□ 口内炎や口角炎ができやすい
□ やる気が出ず、集中力が続かない
□ 神経が過敏になっていると感じる
プロバイオティクス(善玉菌)が不足しているかも?
腸内の善玉菌は“第二の脳”ともいわれる腸の健康を守り、心の安定にも深く関わっています。不足すると便秘や下痢だけでなく、気分の不安定さにもつながることがあります。セルフチェックで確認してみましょう。

□ お腹の調子が不安定(便秘や下痢を繰り返す)
□ 疲れているのになかなか眠れない
□ 理由のない不安感が続く
□ 抗生物質を最近飲んだ
□ 発酵食品をあまり食べていない
当てはまる項目が多かった栄養素は、食事から意識的に補っていくことで、心身の安定につながる可能性があります。
セロトニンを増やす「トリプトファン」

トリプトファンは、体内で合成できない必須アミノ酸のひとつで、脳内の神経伝達物質であるセロトニンの前駆体となります。セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、気分の安定やリラックス効果をもたらし、ストレス耐性を高める働きがあります。
トリプトファンの摂取が不足すると、セロトニンの生成が低下し、不安や抑うつのリスクが高まる可能性があるとされています。実際に、トリプトファンサプリメントを摂取した群は、プラセボ群と比較して不安や抑うつ症状が有意に軽減されたという研究結果があります。
ただし、トリプトファンを含む食品を摂取しただけでは、すぐにセロトニンに変換されるわけではありません。トリプトファンが脳に到達するためには、血液脳関門(BBB)を通過する必要があります。この時に、炭水化物(糖質)を一緒に摂取することでインスリンの分泌が促進され、トリプトファン以外の中性アミノ酸(フェニルアラニン、ロイシンなど)の血中濃度が下がることで、相対的にトリプトファンが脳に取り込まれやすくなると考えられています。
たとえば、バナナ+ヨーグルト、全粒パン+チーズ、豆腐+ご飯などの組み合わせは、トリプトファンの吸収を高めてくれるおすすめの食べ合わせです。
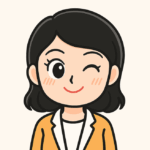 よたきち
よたきち朝、バナナとヨーグルトを一緒に食べるようになったら、午前中の気分が少し穏やかになった気がするよ。手軽だから続けやすいのもいいよね。
- 七面鳥、鶏肉、牛肉、豚肉
- かつお、まぐろ、いわし
- 卵
- 乳製品(ヨーグルト、チーズ、牛乳)
- ナッツ類(アーモンド、カシューナッツ)
- バナナ
- 大豆製品(豆腐、納豆)
ストレス軽減に役立つ「マグネシウム」

マグネシウムは「抗ストレスミネラル」とも呼ばれ、神経の興奮を抑えてリラックスを促す重要な働きがあります。これは、マグネシウムがGABA(γ-アミノ酪酸)の受容体に作用し、脳を落ち着かせる効果を持っているためです。GABAは脳内で「ブレーキ役」として働き、興奮を抑えることでリラックス効果をもたらします。
一方で、マグネシウムが不足すると、神経の興奮を引き起こすグルタミン酸の活動が活発になりすぎて、神経が過敏になりやすくなります。その結果、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が増えることで、不安や緊張感、イライラを感じやすくなる可能性があります。また、マグネシウムが不足すると、睡眠の質が低下し、ストレス耐性が下がる可能性もあります。
さらに、マグネシウムの補給が不安障害やうつ症状の軽減に役立つ可能性を示した研究もあります。あるメタ分析では、マグネシウムを摂取した群はプラセボ群と比較して、不安や抑うつ症状が有意に改善したと報告されています。
しかし、現代人は食生活の乱れや加工食品の摂取増加により、マグネシウム不足に陥りやすいと言われています。特に、ストレスやカフェイン、アルコールの摂取はマグネシウムの排出を促してしまうため、注意が必要です。
食品からの摂取が理想ですが、ダークチョコレート(カカオ70%以上)、ナッツ類(アーモンド、カシューナッツ)、ほうれん草、玄米などに比較的豊富に含まれています。これらを積極的に食事に取り入れることで、不足を防ぎやすくなります。どうしても食事だけで補えない場合は、サプリメントを活用するのも一つの方法ですが、摂取量には注意が必要です。
- 海藻類(あおさ、ひじき、わかめ、海苔)
- ほうれん草、ケールなどの葉物野菜
- アーモンド、カシューナッツ
- かぼちゃの種
- ダークチョコレート(カカオ70%以上)
- 大豆製品(豆腐、納豆)
- ごま
- 玄米、全粒穀物
特にナッツ類やダークチョコレートは、手軽に摂取できるおすすめの食品です。
 よたきち
よたきち私はアーモンドを小分けにして職場に持って行ってましたよ。集中力が切れたときにつまむだけでも、気持ちのリセットになるからおすすめ。
でも正直、毎日ナッツや野菜を欠かさず摂るのは大変なので、私はマグネシウムサプリも取り入れていました。
忙しい毎日の中でここまでバランスよく食事から摂るのはなかなか難しいのが正直なところです。
そんなときに役立つのが、手軽に摂れるサプリメントです。
| タイプ | 商品例 | 特徴 |
|---|---|---|
| コスパ重視 | DHC カルシウム/マグネシウム(DHC) | Ca:Mg=2:1+ビタミンD。手軽&安価。 |
| 国内ブランドの安心感 | ネイチャーメイド Ca・Mg・Zn (大塚製薬) | 厚労省認定の栄養機能食品。Ca・Mg+亜鉛をまとめて摂れる定番品。 |
| まとめて補給したい | ディアナチュラ Ca・Mg・亜鉛・VD (アサヒ) | Ca・Mg・亜鉛+ビタミンD。国内工場生産で安心 |
食生活と合わせて、自分に合うサプリをうまく取り入れてみてくださいね。
炎症を抑え、脳を守る「オメガ3脂肪酸」

オメガ3脂肪酸(EPA・DHA)は、脳の健康をサポートし、不安やストレスの軽減に役立つ重要な成分です。オメガ3脂肪酸には、EPA(エイコサペンタエン酸)とDHA(ドコサヘキサエン酸)があり、それぞれ異なる働きを持っています。
DHAは脳の細胞膜を構成する重要な成分で、神経細胞同士の情報伝達をスムーズにし、脳の認知機能や感情の安定に関わっています。
EPAは抗炎症作用を持ち、脳内の炎症を抑えることで神経の働きをサポートし、不安や抑うつのリスクを軽減する可能性があります。
近年の研究では、オメガ3脂肪酸の摂取が不安症状や抑うつ症状の改善に有効である可能性が示されています。例えば、血中のオメガ3脂肪酸レベルが低い人ほど、不安や抑うつ傾向が強い可能性があることが示されています。また、EPAとDHAを同時に摂取することで、相乗効果が期待できることも報告されています。
オメガ3脂肪酸は体内で十分に合成できないため、食事から積極的に摂る必要があります。魚(サーモン、イワシ、サバ、サンマなど)を週に2〜3回食べることで、十分なEPA・DHAを摂取することができます。
魚をあまり食べない人は、亜麻仁油やチアシード、くるみなどに含まれる植物性オメガ3(α-リノレン酸)も有効ですが、植物性のオメガ3は体内でEPAやDHAに変換される割合が低いため、可能であれば魚や魚由来のサプリメントを取り入れることが推奨されます。
EPAやDHAは酸化しやすいため、新鮮な状態で摂取することが望ましいとされています。グリルや蒸し料理など、低温調理を行うことで栄養素を損なわずに効果的に取り入れられます。
- サーモン、イワシ、サバなどの青魚
- 貝類・甲殻類(ホタテ、カニ、エビ)
- 亜麻仁油、えごま油、チアシード
- くるみ
 よたきち
よたきち魚料理って手間がかかるので忙しいときは敬遠しがちだけど、そんなときは私はサバ缶を使っているよ。手軽にオメガ3脂肪酸(EPA・DHA)を摂取できるし便利なアイテムです。
 ぴょんた
ぴょんた亜麻仁油をサラダにかけるのも手軽でいいよね。
| タイプ | 商品例 | 特徴 |
|---|---|---|
| コスパ重視で手軽に | DHC DHA | DHA・EPAを低価格で摂れる定番サプリ。初心者におすすめ。 |
| 国内大手の安心感(食品メーカー) | 雪印メグミルク DHA&EPA | 1日2粒。魚不足を補うシンプル設計。国内乳業大手の信頼性。 |
| 高級志向・機能成分追加 | サントリー DHA&EPA+セサミンEX | DHA・EPAにセサミン・ビタミンEを配合。やや高価だがブランド力◎。 |
| 続けやすさ&国内品質 | ディアナチュラDHA | マグロから抽出した精製魚油を使用。DHA 350mg+EPA 45mgを配合。大手食品メーカー製で安心して続けやすい。 |
DHAサプリの中でもよたきちのオススメはこれ!
効果・安全性・価格の三拍子を考えると、ディアナチュラスタイル DHA(アサヒ) が圧倒的におすすめです。
国内大手食品メーカーの安心感がありつつ、DHA・EPAを適切に補える価格帯。

神経の安定を助ける「ビタミンB群」

ビタミンB群は、エネルギー代謝を助けるだけでなく、神経の働きを正常に保ち、脳の健康を支える重要な栄養素です。ビタミンB群には8種類(B1、B2、B3(ナイアシン)、B5(パントテン酸)、B6、B7(ビオチン)、B9(葉酸)、B12)があり、それぞれが脳と神経の機能に重要な役割を果たしています。特に以下の3つは、不安や抑うつ症状の軽減に重要な役割を果たしていると考えられています。
①ビタミンB6(ピリドキシン)
ビタミンB6は、気分を安定させるセロトニンやドーパミン、GABAなどの神経伝達物質の合成に関与しています。不足すると神経伝達がうまくいかず、不安やイライラが増しやすくなります。また、ビタミンB6は女性の月経前症候群(PMS)の症状緩和にも効果があることが示されています。
②葉酸(ビタミンB9)
葉酸は、脳内の神経細胞の修復や再生を助けるほか、ホモシステインというアミノ酸の代謝にも関与しています。ホモシステインが過剰になると脳機能に悪影響を及ぼし、抑うつや認知機能低下のリスクを高めることが示されています。研究では、葉酸の適切な摂取がうつ症状の軽減に関連している可能性があると報告されています。
③ビタミンB12(コバラミン)
ビタミンB12は、神経細胞を保護し、ミエリン鞘(神経を覆う絶縁体)の維持に重要な役割を果たします。不足すると神経の働きが低下し、不安や抑うつの症状が現れることがあります。また、赤血球の生成にも関与しており、不足すると貧血や疲労感につながります。
効果的な摂取方法
ビタミンB群は水溶性で体内に蓄積されにくいため、毎日の食事で継続的に摂取することが重要です。特にストレスが多いと消費量が増えるため、不足しやすくなります。動物性食品に多く含まれるビタミンB12は、ベジタリアンやビーガンの方が不足しやすいため、必要に応じてサプリメントを活用するのも一つの方法です。
- ビタミンB6 → 鶏肉、鰹、鮭、マグロ、バナナ、じゃがいも
- 葉酸 → ほうれん草、とうもろこし、枝豆、納豆、いちご
- ビタミンB12 → 肉類(特にレバー)、卵、乳製品、魚介類、海藻類
 よたきち
よたきち私は疲れがたまってるときは、納豆と卵の組み合わせをよく食べてるよ。どちらにもビタミンBが入ってて、元気の回復にもつながる感じがするよ。
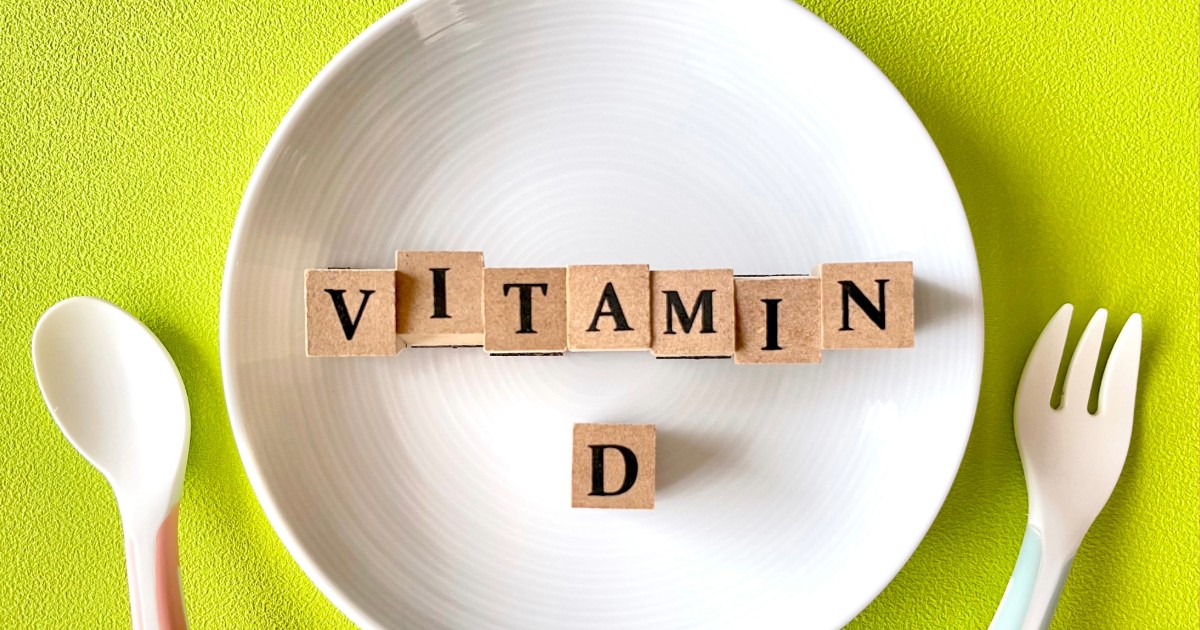
腸内環境を整えてメンタルを安定させる「プロバイオティクス」

腸と脳の密接な関係を指す「腸脳相関」は、近年の研究で注目されています。腸内環境が脳の健康に影響を与えることが確認されており、特に腸内細菌がセロトニンの生成に重要な役割を果たしていることが知られています。セロトニンは気分や不安感を調整する重要な神経伝達物質ですが、その約90%が腸内で生成されています。
腸内に存在する腸内細菌がトリプトファンを代謝し、腸クロム親和性細胞(EC細胞)を通じてセロトニン合成を促進しています。腸内フローラのバランスが乱れるとセロトニンの生成が低下し、不安感や気分の不安定さにつながる可能性があります。
腸内環境を整える方法として、プロバイオティクス(腸内の善玉菌)とプレバイオティクス(善玉菌のエサ)の摂取が効果的です。
- ヨーグルト、納豆、キムチ、味噌
- チーズ、ぬか漬物
- 野菜(ごぼう、にんじん、玉ねぎ)
- 果物(バナナ、リンゴ)
- 全粒穀物(玄米、オートミール)
 よたきち
よたきち私は夜ごはんに味噌汁を飲むようにしています。
発酵食品を摂ると「ちゃんと食事しているな」と思えて、心が落ち着くんです。
でも遅くまで働いている私にとって、毎日食事から必要な菌を摂るのはなかなか大変。
そんなときにいくつか試した中で、一番実感できたのがビオスリーでした。続けていると、日々の体調が安定してきたのを自分でも感じていま
す。
整腸剤の中でもよたきちのオススメはこれ!
ビオスリーの特徴は、乳酸菌(ラクトミン)に加えて、酪酸菌と糖化菌を組み合わせた「3つの菌のトリプル配合」にあります。
一般的な整腸剤は乳酸菌だけを含むものが多いのですが、ビオスリーはそれぞれ異なる働きを持つ菌を組み合わせているため、腸内環境をより幅広くサポートできるのです。結果として、腸にバランスよく定着しやすいのが大きな強みです。
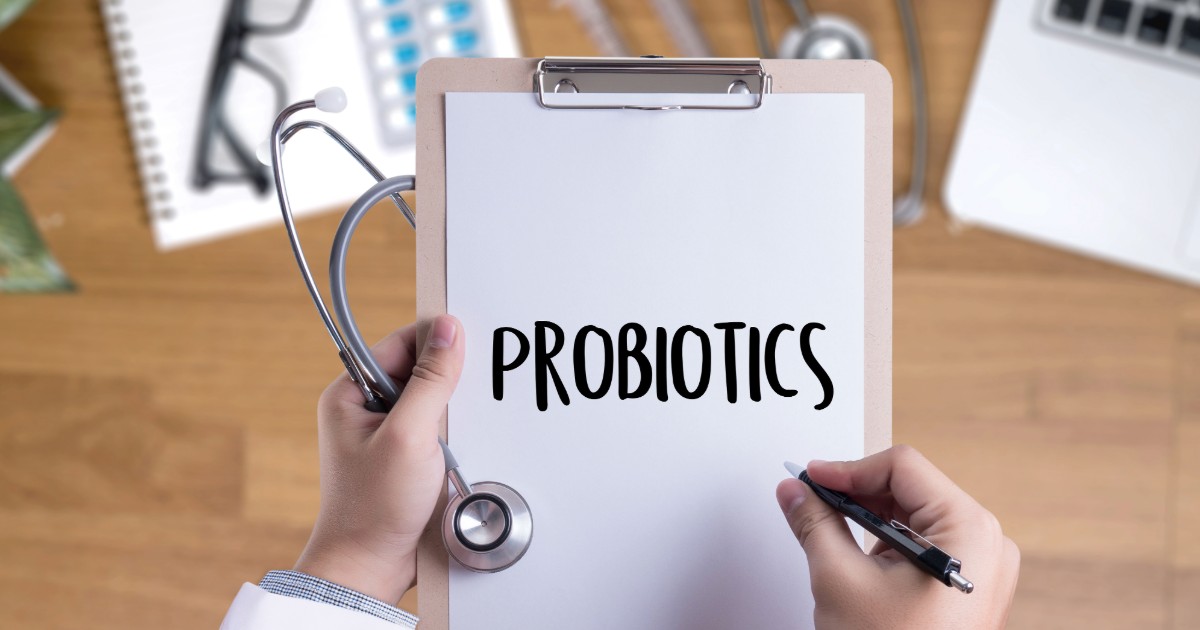
まとめ :食事でメンタルケアを
不安が強いとき、体に出るサインから、自分の不調に気づくことがあります。
食欲がない、疲れやすい、寝つけない――そんなときは、無理に元気を出そうとせず、まず「今日は何を食べるか」を考えてみてください。
バナナ1本でも、温かい味噌汁でも、それだけで少し気持ちが落ち着くことがあります。
食べることは、ただ栄養を摂るだけでなく、自分の心にエールを送る行動でもあります。
完璧な食事じゃなくても構いません。
「心に栄養をあげるつもりで食べてみる」それだけで十分です。
食べることが、気持ちを立て直すきっかけになりますように。