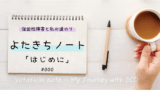犬や猫は、私たちの生活を豊かにしてくれるかけがえのない存在です。しかし、そんな身近な家族の行動に「ちょっとおかしいかも?」と感じる瞬間はありませんか?
実は、人間だけでなく、ペットにも「強迫性障害(OCD)」のような症状が見られることがあります。動物の世界ではこれを「常同行動(じょうどうこうどう)」と呼び、精神的ストレスや遺伝的素因が関係していると考えられています。
本記事では、動物に見られる常同行動の特徴や原因、治療法までを、専門的な視点を交えながらわかりやすく解説します。
1. 動物の強迫性障害とは?

人間の強迫性障害と似たような症状が、犬や猫といった動物にも現れることがあります。これらの行動は、医学的には「常同行動(stereotypic behavior)」と呼ばれ、特に以下のような特徴を持ちます。
- 目的がなく、同じ行動を延々と繰り返す
- 中断しづらく、他の刺激に対する反応が乏しい
- ストレスや不安と関連して出現することが多い
代表的な常同行動の例
犬の場合:
- 尾を追ってぐるぐる回る
- 体の一部を過剰に舐め続ける(皮膚炎を伴うことも)
- 空中に向かって吠え続ける
- 同じ経路を何度も往復する
猫の場合:
- 同じ部位を執拗にグルーミング(毛づくろい)する
- 家の中を特定のパターンで歩き回る
- 壁や家具を繰り返し引っかく
これらの行動は、一見すると癖や遊びのように見えるかもしれません。しかし、それが生活に支障をきたすほど継続的で強迫的な場合、「異常行動」としての対応が求められることもあります。
2.なぜ起こるのか?常同行動の背景にある3つの要因

①環境的ストレス
運動不足や退屈、孤独など、日常の刺激が足りない生活環境がペットにストレスを与え、それが常同行動の引き金になります。たとえば長時間の留守番、引っ越しなどの生活環境の変化、家庭内の緊張状態などが挙げられます。
②遺伝的素因
特定の犬種や猫種には、常同行動が起こりやすい傾向があることが知られています。たとえば、柴犬やドーベルマン、シェパードなどでは、尾追いや舐め行動がよく見られます。猫では、バーミーズなどがグルーミング過多を示すことがあります。これには脳内の神経伝達物質(特にセロトニン)の調整不全が関与しているとされます。
③健康状態や過去のトラウマ
痛みや病気、不快感が常同行動の背景にあることも少なくありません。たとえば関節痛をかばうために足を舐め続けたり、過去に受けた虐待の記憶から回避行動を繰り返したりと、心と体が深く関係しています。
3.ペットと強迫性障害の研究動向
動物の強迫行動と飼い主の生活環境との関連性については、複数の研究が行われています。例えば、スウェーデンのリンショーピング大学の研究では、飼い主と犬のコルチゾール(ストレスホルモン)レベルが長期的に同期していることが報告されています。この研究では、飼い主が慢性的なストレス状態にある場合、犬も同様に高いストレスレベルを示すことが確認されました。
また、麻布大学の研究では、犬のメラノコルチン2受容体遺伝子の変異が、人とのコミュニケーション能力や社会的認知能力に関連していることが示唆されています。この研究では、遺伝的にオオカミに近い犬種とそうでない犬種を比較し、特定の遺伝子多型が人への依存行動やコミュニケーション能力に影響を与える可能性があることが示されました。
これらの研究から、動物の行動は単なる個性やしつけの問題ではなく、「脳」「環境」「飼い主の影響」といった多層的な要因の交錯によって成り立っていることがわかります。
4.診断と治療:どう向き合うべきか?
①診断のポイント
獣医師や動物行動学の専門家は、ペットの日常的な行動や健康状態を細かく観察し、行動パターンの変化や反復的な行動をチェックします。急激な行動の変化や、通常とは明らかに異なる行動が続く場合、獣医師が診断の一環として強迫性障害の可能性を検討することがあります。
②治療法と対策
- 環境改善:適度な運動や遊びの時間、そして精神的な刺激を与えることで、ストレスを軽減することが重要です。
- 行動療法: 獣医師や動物行動専門家によるカウンセリングやトレーニングが有効とされています。ポジティブな行動を促すために、環境の調整が必要になることがあります。
- 薬物療法: 症状が重い場合には、抗不安薬やその他の薬剤が処方されることがあります。治療には獣医師と密接に連携することが重要です。
5. まとめ
ペットの常同行動は、単なるしつけの問題や「癖」ではありません。
その背後には、私たちが気づいていないストレスや不安、時には病気やトラウマが隠れていることもあります。
大切なのは、「なぜこの行動をするのか?」という視点を持ち、ペットの立場に立って考えることです。行動を注意深く観察し、早めに専門家に相談することで、ペットの心と体の健康を守ることができます。
ペットは言葉を持たないぶん、行動によって私たちにメッセージを送っています。
その“沈黙のサイン”に耳を傾け、共に安心して過ごせる環境を整えていきましょう。