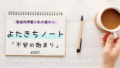朝の目覚めに一杯。仕事や勉強の合間にもう一杯。コーヒーは、いまや多くの人の生活に欠かせない存在になっています。
そんななか、強迫性障害(OCD)を抱える人の中には、
「コーヒーを飲んだあと不安感が強くなった気がする」「思考が止まらず、頭の中がざわつく感じがする」といった違和感を覚える人も少なくありません。
実は、コーヒーの成分であるカフェインと、強迫性障害の神経的な特徴には、意外なつながりがあるかもしれないのです。
1.覚醒だけじゃない?カフェインの“二面性”

コーヒーに含まれるカフェインは、中枢神経を刺激して眠気を抑える作用で知られています。
これは、脳の「ブレーキ役」である神経伝達物質アデノシンの働きをブロックすることで、眠気を抑え、頭をスッキリさせる効果があります。
ところが、カフェインにはこの覚醒作用とともに、交感神経を活性化し、不安感や緊張を高める作用もあるのです。
動悸がしたり、落ち着きがなくなったり、イライラを感じたりするのは、脳が「興奮しすぎた」状態だからです。
つまり、カフェインは「目を覚ます」だけでなく「神経を過敏にさせる」面もあわせ持っているのです。
2.強迫性障害の“過敏な脳”にとって、カフェインはどう働く?

強迫性障害では、脳内ネットワークの過剰な活性化が指摘されています。
なかでも、「扁桃体(へんとうたい)」と呼ばれる恐怖反応を司る部位が過敏になりやすく、
また、セロトニンの調整機能に問題があることがわかっています。
こうした“もともと興奮しやすい神経系”に、さらにカフェインという刺激が加わると、
- 頭の中で同じ思考がぐるぐる回る
- 「確認したい」衝動が強くなる
- 不安感が高まって収まらない
といった症状が悪化する可能性があるのです。
つまり、“もともと敏感になりやすい脳”にカフェインという火種が加わるイメージです。
わずかな刺激でも、神経が過剰に反応してしまうことがあります。
3.個人差も大きい:カフェイン感受性は人それぞれ

とはいえ、カフェインへの反応には個人差があります。
その一因は、遺伝的な体質、特にカフェイン代謝能力にあります。
たとえば、「CYP1A2」という肝臓の酵素の働きが強い人はカフェインをすぐに分解できますが、そうでない人は長時間体内に残ってしまいます。
つまり、「コーヒー1杯で不安感が高まる人」と「5杯飲んでも平気な人」がいるのは、脳の感受性だけでなく代謝の違いも影響しているのです。
さらに、毎日コーヒーを飲むと、体がカフェインに慣れ(耐性がつき)やすくなります。
この場合、飲まないときに逆にイライラ感や不安感が強まる「離脱症状」を感じることもあります。
また、「デカフェ(カフェインレス)」と書かれていても、ごく少量のカフェインは含まれているため、極度に敏感な人は注意が必要です。
4.無理にやめなくてもOK。大事なのは“タイミング”

ここで気になるのが、
「強迫性障害の傾向があるなら、コーヒーはやめた方がいいの?」という疑問です。
結論からいえば、「人によるけれど、見直してみる価値はある」でしょう。特に、不安が高まりやすい時期や、確認行動が止まらないと感じるときには
- 朝の1杯だけにする
- 空腹時は避ける
- デカフェに切り替えてみる
- 数日間だけ試しにカフェインを断ってみる
といった工夫が、神経の落ち着きにつながることがあります。
5.「好き」と「負担」のバランスを自分で見つけよう

コーヒーは、リラックスや集中の助けになる一方で、神経を刺激して負担をかけることもあります。大切なのは、「いま自分にとって、どちらに働いているか?」を見極めること。
もし、コーヒーを飲んだあとに毎回、「不安が強くなる」「思考が止まらない」と感じるなら、それは体が出している小さなサインかもしれません。
6.さいごに
コーヒーと強迫性障害の関係についての研究は、まだ発展途上です。
しかし、「日々の何気ない習慣が、心にどんな影響を与えているか?」に気づくことは、自分をよりよく理解する大きなヒントになります。
ほんの少し飲み方を変えるだけで、気持ちが穏やかになったり、思考がクリアになったりするかもしれません。あなた自身に合ったコーヒーとの付き合い方を、ゆっくり探していきましょう。